子どもの自己肯定感は、成長過程での心の健康や将来の自信に大きな影響を与える重要な要素です。しかし、日々の接し方次第で自己肯定感が低下してしまうケースもあります。
本記事では、子どもの自己肯定感を高めるためのポイントや注意しなければならない点について解説しています。また、よくある質問も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
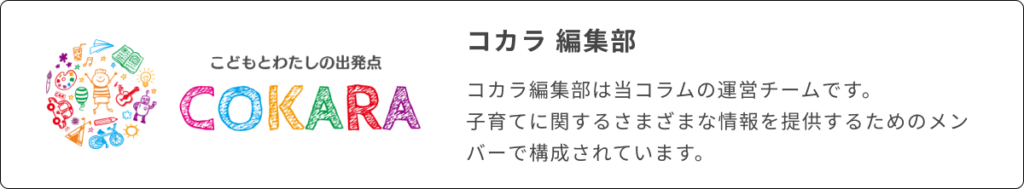

自己肯定感とは?
自己肯定感は、自分を受け入れ、前向きに行動するための重要な要素です。自分を尊重し肯定的に捉えられる人は、困難な状況に直面しても自信を持って対応できる傾向があります。
また、自分に対して満足感があると、他者を尊重する心を育み、人間関係を良好に保つ助けとなります。しかし、自己肯定感は一朝一夕に築かれるものではありません。
特に子どもの成長過程では、周囲の大人が温かく接し、失敗を恐れない環境を整えることが大切です。日々の小さな成功や努力を認め合えれば、自然に自己肯定感が育まれます。
自己肯定感が高い子どもの特徴
子どもが自分らしく成長していくためには、日々の中で信頼や肯定感を育む環境が大切です。たとえば、自分の気持ちを正直に伝えられる場面や、物事に前向きに挑戦する姿勢を大人が温かく見守ると、子どもは自信を持って行動できるようになります。
また、失敗を恐れず挑戦し続ける力は、周囲の支えや理解によって強くなります。他人を尊重し感謝の気持ちを持つことは、円滑な人間関係を築くための大切な基盤です。
子どもが壁にぶつかる場面があれば、そばにいる大人が丁寧に向き合い、励ますことが大切です。
自己肯定感が低い子どもの特徴
新しいことに挑戦する際に不安を抱くことは、誰にでもある自然な感情です。しかし、その不安が過剰になると、物事を悲観的に捉えたり、自分を責めたりする傾向が強まるケースがあります。
失敗を恐れるあまり、チャンスに背を向けたり、挑戦を避けたりしてしまう場合、自分の可能性を狭めてしまうかもしれません。また、他人との比較で劣等感を抱くと、自己否定が強まり、人間関係にも影響が及ぶ場合があります。

子どもの自己肯定感を高めるためポイントは3つ
次に、子どもの自己肯定感を高めるためのポイントをご紹介します。
- 子どもを褒めてあげる
- 失敗しても前向きな声かけをする
- 子どもに意見を求めてみる
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.子どもを褒めてあげる
子どもを褒める際には、結果だけでなく、努力や工夫に目を向けることが重要です。たとえ結果が思わしくなくても、頑張った過程を認めてあげると、子どもは自分の行動に自信を持てます。
具体的な行動や姿勢を褒めるのは、子ども自身が何を評価されたのか理解しやすくなるため、次の挑戦への意欲を高める効果的な方法です。一方、結果のみを強調すると、失敗を恐れるようになったり、周囲の反応を過剰に気にする傾向が強くなります。
また、努力を称賛すると、子どもは自分の価値を見出し、主体的に行動する力を育んでいけます。
2.失敗しても前向きな声かけをする
子どもが失敗したときには、その努力を認め、温かい言葉をかけることが大切です。「今回はうまくいかなかったけど、すごく頑張ったね」「もう一度挑戦してみよう」といった声掛けをすると、子どもは失敗を怖がることなく、次の挑戦に向かう勇気を持てます。
このようなサポートで、子どもに「自分は大切にされている」という安心感を与えるのが、自己肯定感を育むポイントです。また、失敗を1つの学びと捉えられるようになると、成長する力も高まります。
3.子どもに意見を求めてみる
子どもの行動には、その背後に子どもなりの考えや理由があるものです。そのため、行動が理解しづらい場合でも、まず子ども自身に「どうしてそうしたのか」を尋ねることが大切です。
子どもの考えを聞く姿勢を示すと、相手に対する尊重の気持ちが伝わり、子どもの自己肯定感が育まれます。また、意見を聞く際には、相手が安心して話せる環境を整えるのもポイントです。
話を聞くだけでなく、質問を交えたり、相槌を打ったりして、相手が理解されていると感じるコミュニケーションを心がけると、より深い信頼関係を築けます。子どもの声に耳を傾ける姿勢が、成長を支える基盤になります。

子どもの自己肯定感を高めるために注意しなければならない点は3つ
次に、子どもの自己肯定感を高めるために注意しなければならない点をご紹介します。
- 言動や人格を否定しない
- 怒ったり怒鳴ったりしない
- 正論責めにしない
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.言動や人格を否定しない
子どもが間違った行動をした場合、叱る際の言葉選びには注意が必要です。「どうしてそんなことをしたの?」と、まずは子どもの気持ちを尋ねると、背景にある理由を理解しやすくなります。
一方で、「そんなことをする子なんて信じられない」などと、子どもの人格を否定する言葉は避けるべきです。そうした言葉は、子どもの心を傷つけ、自己肯定感を大きく損なう可能性があります。
行動そのものを指摘し、どのように改善すべきかを具体的に伝えると、子どもは自分を受け入れながら成長できます。
2.怒ったり怒鳴ったりしない
子どもが間違いを犯したとき、感情的に怒鳴るのではなく、冷静に対応することが大切です。怒鳴られた経験は子どもの心に強い印象を残し、「また怒られるかもしれない」と感じて行動を控えるようになる場合があります。
その結果、新しいことに挑戦する意欲や自分を肯定する気持ちが損なわれてしまうケースがあります。一方で、穏やかに話を聞きながら子どもの意見や気持ちを受け止めるのは、子どもに安心感を与える接し方です。
このような対応は、子どもが自身の行動を振り返り、次にどうすれば良いのかを考える力を育てるだけでなく、自己肯定感を高める土台となります。
なお、子どものしかり方については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
関連記事:子どものしかり方は?気をつけたいことからしかるときのポイントまでご紹介します – コカラ
3.正論責めにしない
成長途中の子どもに対して、完璧を求めすぎるとかえって逆効果です。保護者の「こうしてほしい」という期待が強すぎると、子どもは自分に自信を持てなくなり、「何をしてもダメなんだ」と感じてしまいます。
注意が必要な場面では、正論で子どもを追い詰めるのではなく、自分の気持ちや考えを穏やかに伝えるよう心がけましょう。「私はこう感じたよ」「こうしてくれたら嬉しいな」といった言葉を使うと、子どもも受け入れやすくなります。

子どもの自己肯定感でよくある3つの質問
最後に、子どもの自己肯定感についてよくある質問をご紹介します。
- 子どもの自己肯定感には「保護者の接し方」が関係するの?
- 子どもの自己肯定感が低いとどのような影響がある?
- 自己肯定感が下がっているサインとは?
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1.子どもの自己肯定感には「保護者の接し方」が関係するの?
子どもの自己肯定感は、日常生活の中での関わり方や環境によって少しずつ形作られます。特に、家庭での保護者の言葉や態度は大きな影響を与えます。
たとえば、否定的な言葉を頻繁に耳にすると、子どもは無意識に自分を否定的に捉えるようになりがちです。一方で、「頑張っているね」「挑戦したことがすごいね」といった言葉をかけられると、失敗を恐れず挑戦し続ける意欲が高まります。
ただし、家庭だけがそのすべてを担うわけではありません。学校や習い事、友人との交流など、心理的安全性が確保されたさまざまな場面で自己肯定感が育まれます。
質問2.子どもの自己肯定感が低いとどのような影響がある?
自己肯定感とは、自分をありのままに受け入れ、肯定的に捉える感覚を指します。この感覚が高い子どもは、物事に積極的に挑戦し、自分の意見をしっかりと伝えられます。
一方、自己肯定感が低い場合陥りやすいのは、「どうせ自分なんて」といった否定的な考えになり、新しい物事に挑戦する意欲を失うケースです。
さらに、自己肯定感が低い状態が続くと、大人になってからも他人に依存しやすくなったり、些細な出来事でも不安を抱えたりと、生きづらさを感じる場面が増える場合が考えられます。
自己肯定感は、親の接し方や周囲の関わり方が大きく影響します。日常の中で子どもの努力や存在を認め、温かく接するのが、この感覚を育む基盤です。
質問3.自己肯定感が下がっているサインとは?
自己肯定感が低いと感じる場面があっても、過度に心配する必要はありません。親子の関わり方を少し意識するだけで、子どもは安心感を得て自己肯定感を育めます。
たとえば、学校や習い事、宿題など日々のタスクが多すぎると、子どもが評価を気にしすぎたり、プレッシャーを感じたりする場合があります。生活の中で「頑張りすぎていないか」を見直し、少し余裕を持たせてあげることが大切です。
また、子どもが抱える不安や困りごとをじっくり聞く時間を作ると、子どもは「自分の話を大切にされている」と感じ、自信を持ちやすくなります。小さな日常の積み重ねが、子どもの心を豊かにします。

まとめ
本記事では、子どもの自己肯定感を高めるためのポイントと注意しなければならない点について解説しました。
自己肯定感を育むためには、子どもの努力や行動を認める、否定的な言葉を避ける、そして成功体験を積ませてあげる環境が大切です。
一方で、完璧を求めすぎたり、他人と比較したりするのは、自己肯定感を低下させる原因となるため注意が必要です。子どもの感情や意見を尊重しながら接すると、安心感を与え、前向きに挑戦できる力を育んでいけます。
これらのポイントを意識すると、子どもたちが自信に満ちた未来を築く手助けとなります。親子関係を深めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
なお、次のページでは、イヤイヤ期の子どもへの接し方のコツや注意すべきポイントを紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
関連記事:イヤイヤ期の子どもへの接し方のコツは3つ|自己主張する原因や注意すべきポイントを紹介!
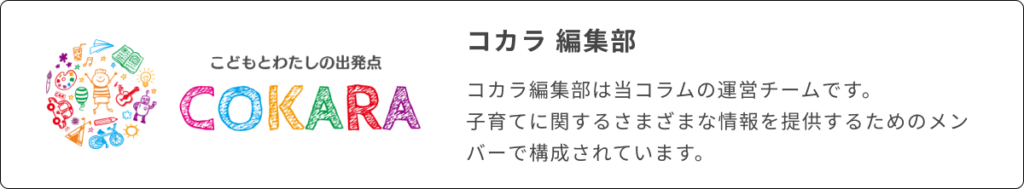



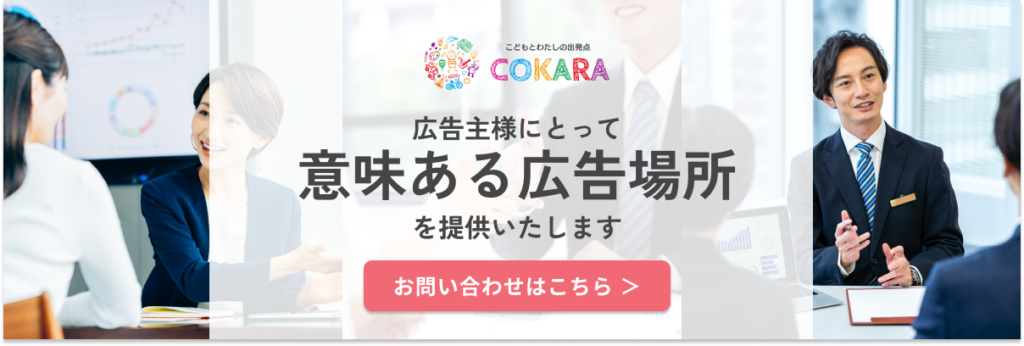
コメント