子どもが誤った行動をしたときに、親はきちんとしからなければなりません。しかし、しかり方を間違えてしまうと、子どもに真意が伝わらず逆効果になる恐れがあります。この記事では、子どもをしかるときに気をつけたいことから、注意しておきたいポイントまで解説します。
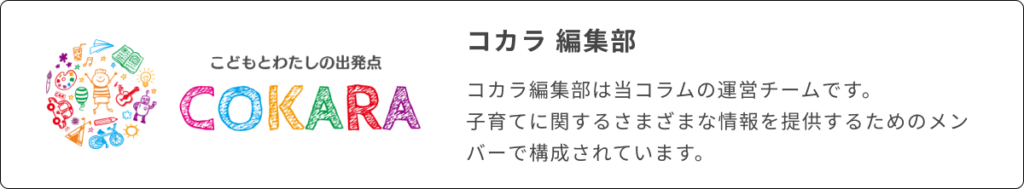

子どもをしかる理由は?
子どもをしかるのは、以下のようにさまざまな理由があります。
- 自分の命を守る
- 他人を傷つけない
- 集団や社会のルールを学ぶ
- 自分勝手な言動を律する
子どもは生活のなかでルールを学びます。親としては当然のことでも、子どもからすると分からない場合も考えられるでしょう。
特に命に関わるような行動を取った場合には、きちんとしからなければなりません。しかったことで子どもに親の想いが通じたときは、褒めてあげるように心がけましょう。

子どものしかり方で気をつけたい3つのこと
子どものしかり方で気をつけたいことには、以下の3つが挙げられます。
- しかった理由を必ず伝える
- 目を見て話す
- しかる基準を決めておく
子どもも1人の人間です。そのため、理不尽なしかり方をされると親の真意が伝わりにくくなります。ここでは、しかり方で気をつけたいことを解説します。
1.しかった理由を必ず伝える
子どもをしかるときは、必ず理由を伝えましょう。特に小さな子どもは、なぜしかられたのか、しかられただけでは理解していないおそれがあります。そうなると、また同じ過ちを繰り返してしまうかもしれません。
そのため子どもをしかるときは、ていねいに理由を説明しながら子どもに言い聞かせてあげてください。子どもが納得すれば成長につながります。
2.目を見て話す
子どもをしかるときは、目を見て話すことも大切です。片手間でしかっても子どもには伝わらないでしょう。また、目を見てしかる場合、子どもの目線に合わせるように意識してください。
大人の視線から見下ろすようにしかってしまうと、子どもは威圧感を覚えてしまいます。「目は口ほどにものをいう」との言葉があるように、子どもは親の目からたくさんの感情を読み取っています。しっかりと目を見ることで親からの愛情を感じ、しかられたことを受け入れやすくなるでしょう。
3.しかる基準を決めておく
しかる行為は、子どものためにすることです。そのため、親のフラストレーションを発散するようなしかり方は避けるべきです。
たとえば、昨日はしかられなかったことを今日はしかられたような場合、子どもは「親の機嫌が善悪の基準」と誤った認識を持つおそれが高まります。
このようなことを防ぐためには、日頃からしかるときの基準を定めておく必要があります。一貫性のある基準があれば、子どもはしかられたとしても納得しやすくなるでしょう。

子どものしかり方で避けるべき3つのこと
子どものしかり方で避けるべきことには、以下の3つが挙げられます。
- ほかの子どもと比べない
- 怒鳴る
- 叩く
子どもをしかるときは、萎縮させるような態度や言動は控えましょう。子どもを萎縮させてしまうと、その場凌ぎにしかならず成長につながりません。
1.ほかの子どもと比べない
ほかの子どもと比べてしかることは、子どもの劣等感を高めるおそれがあります。
このようなしかり方をすると「僕・私はダメな人間なんだ」「人よりも劣っているんだ」といった気持ちが積み重なりやすく劣等感に支配された大人に成長しやすくなります。
子どもを比べるのであれば、過去・未来の本人と比較すると良いでしょう。たとえば「おもちゃが片付けられたらかっこいいお兄ちゃんになれるね」や「前は〇〇ができなかったのに、できるようになってすごいね」と時間軸を意識した声かけが有効です。
2.怒鳴る
感情的に怒鳴る行為は避けてください。感情に任せて怒鳴る行為は、自分の怒りや腹立ちを相手にぶつけているに過ぎません。
一方、しかる行為は子どもを諭して正しい方向に導くことが目的です。そのため、大声で怒鳴ると子どもは萎縮し、逆効果になる恐れがあります。その場では親の言うことを聞くように振る舞うかもしれませんが、正しい方向に導くことはできません。
3.叩く
叩くしつけは心や体に傷を与える体罰です。体罰は子どもに大きな恐怖心を植え付けることになり、絶対に控えるべきです。恐怖心は生涯にわたり心に影を落とすおそれがあるでしょう。
また、自分が子どもの頃「叩かれてしつけられた」という親は注意が必要です。自分の経験から衝動的に叩いてしまいそうな人は、怒りの感情が沸いたときに子どもから距離を置いて、自分の感情を落ち着かせてからしかるように意識してみてください。

【年齢別】子どものしかり方のポイント
子どもをしかるときは、年齢や発達に合わせて伝え方を変えることが重要です。年齢ごとの子どもの傾向や効果的なしかり方を以下の3通りに分けて解説します。
- 0〜1歳
- 2〜3歳
- 4〜6歳
子どもが小さい頃はなるべくしからないように意識し、成長とともに自分自身で考えられるように仕向けることがポイントです。ここではそれぞれの年齢に合わせてしかるときに意識したいポイントを解説しますので、見ていきましょう。
0〜1歳
0〜1歳児はまだ言葉での意思疎通が十分に行えないため、親はしかっても子どもはわからないだろうと考えてしまいがちです。しかし、子どもは声色や目を見て大人が怒っているのかを判断しています。
悪いことをしているのを見つけたときは、その場で視線を合わせて短時間でしかるように意識しましょう。しかるときはいつもよりも声のトーンを低くすると、子どもに「しかられている」と伝わります。
とはいえ0〜1歳児は親がしかる意図や意味をくみ取ることは難しいため、親がしからないで済むような環境整備を心がけましょう。
2〜3歳
2〜3歳になるとイヤイヤ期に入る時期となり、しかりたくなることが増えてしまうでしょう。しかりたくなるような行動としては、兄弟や友達に暴力を振るう、駄々をこねて遊び場から離れないなどが挙げられます。
親のいうことを嫌だと感じやすい時期のため、しかるよりも先に子どもの気持ちに寄り添ってから、生活に必要な決まりごとをわかりやすく伝えるようにしましょう。
4〜6歳
4〜6歳頃になると、大人のいうことや周囲の状況を理解できるようになります。そのため、しかる場合は理由を説明し、一貫性を持った対応を心がけることが重要です。同じ行動を取ってもしかったりしからなかったりすると、子どもを混乱させてしまいます。
また5〜6歳になれば、ただ正しい行動を教えるだけでなく、自分で考えさせるようにすることも大切です。この頃になると「恥ずかしい」という気持ちが芽生える時期でもあるので、しかるときは2人きりになるように配慮してあげましょう。

しかっても聞いてくれないときに意識したい3つのこと
子どもをしかっても言うことを聞いてくれない場合、以下の3つを意識しましょう。
- ほかのことをさせる
- 親が手本を示す
- 本当にしかるべきか考える
しかられるような行動の裏には子どもの本音が隠れているかもしれません。ここではそれぞれにポイントを分けて意識したいポイントを解説します。
1.ほかのことをさせる
子どもがしかりたくなるような行動を取る場合、親からの注目を集めたい気持ちがあるのかもしれません。そのような気持ちで取った行動をしかるだけにすると、子どもが塞ぎ込んでしまう可能性があります。
このときにはしかると同時に、他の行動に仕向けることをおすすめします。たとえば、家事をしているときにこどもが困った行動をしたら「〇〇を一緒にしよっか?」と声をかけて意識を逸らしてあげるとよいかもしれません。
2.親が手本を示す
子どもをしかるときは、しかったあとにどのように行動してほしいか手本を示すようにしてあげましょう。子どもは、しかられて行動を止められたとしても、次にどうすればよいのか分からない場合があります。
しかったあとにすぐ「してほしい行動」の手本や言葉で説明することで、正しい行動を身につけやすくなるでしょう。
子どもは親の日常的な行動をよく観察しています。親自身が日頃から手本となるような行動を心がけることも重要です。
3.本当にしかるべきか考える
子どもの発達段階に合わせて、本当にしかるべきなのかを考えることも大切です。あまり小さいうちからしかりすぎると、親の顔色をうかがう癖が身についてしまうおそれもあります。
また、本来しかるという行為は、子どもを正しい行動に導くことが目的です。子どもの発達段階やそのときの状況に合わせてしかるように意識しましょう。

子供 しかり方でよくある5つの質問
子供のしかり方でよくある質問には、以下の5つが挙げられます。
- 質問1.正しい叱り方で得られるメリットとは?
- 質問2.子育てでイライラが抑えられない場合は?
- 質問3.子どもが言うことを聞かない場合は?
- 質問4.子どもが嘘をつく心理とは?
- 質問5.子育てを楽しむには?
ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
質問1.正しい叱り方で得られるメリットとは?
正しい叱り方で得られるメリットには、以下のようなものが挙げられます。
- 命の安全を守る:命に関わる危険な行動に対して、正しく叱ることで子どもの危機管理能力を高められる
- 他人を傷つける行為を防ぐ:人を傷つける行為を「絶対にしてはいけないこと」として教え、暴力や暴言の防止につなげる
- 社会のルールがわかる:社会のルールを理解し、社会的な問題行動を未然に防ぐために必要な教育ができる
質問2.子育てでイライラが抑えられない場合は?
子育てにおけるイライラの対処法には、以下のようなものが挙げられます。
- 怒りのひとつ前の気持ちに意識を向ける:イライラする直前の感情に気づき、早めの対処を図る
- イライラしている自分を認める:自己の感情を受け入れ、無理に抑え込まない
- たまには自分にご褒美を与える:ストレスを軽減するために、自分へのご褒美を設定する
- イライラの本当の原因を知る:根本的な原因を探り、解決策を見つける
- できていることに目を向ける:成果や進歩に焦点を当て、前向きな気持ちを育む
また、子育てのイライラを抑えられない場合の対処法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
関連記事:子育てでイライラが抑えられない人のタイプとは?爆発しないための対処法も理解しよう! – コカラ
質問3.子どもが言うことを聞かない場合は?
子どもが言うことを聞かない場合の対処法には、以下のようなものが挙げられます。
- 親が約束を守る
- 子どもの気持ちに寄り添う
- 子どもの意見に耳を傾ける
- 脅すような言葉は使わない
- 代替案を考えてみる
- ダメな理由を添えて伝える
- 一貫性のある言動を心がける
また、子どもが言うことを聞かない場合の理由や正しい対処法については以下の記事で解説しています。気になる方はぜひ参考にしてみてください。
関連記事:子どもが言うことを聞かない理由を年齢別に解説!正しい対処法も紹介します – コカラ
質問4.子どもが嘘をつく心理とは?
子どもが嘘をつく理由には、心理的な背景があります。子どもは「これ以上叱られたくない」という気持ちから咄嗟に嘘をついてしまいます。
そのため、嘘をついたことを叱るのではなく、子どもの話を受け止めることが重要です。その後、子どもへ嘘をつかないことの重要性を伝えるようにしてください。
また、子どもが嘘をつく原因が親にある場合は、それを取り除くことから始めなければなりません。
質問5.子育てを楽しむには?
子育てを楽しむには、以下のポイントを意識してください。
- 他人と比べない
- 子どもをコントロールしようとしない
- 子どもに集中してみる
- 育児の悩みを共有できる居場所を作る
- 今、この瞬間を大切にする
子育てはどうしても他所と比較してしまいがちです。しかし、自分と子どもは唯一無二のものであるため、本来は比べようがありません。
子育てを楽しめない・楽しむコツについては以下の記事で詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:子育てを楽しむには?子育てを楽しめない理由や楽しむためのコツをご紹介 – コカラ

まとめ
子どものしかり方について解説しました。子どもをしかるときは、自分の感情を出すのではなく「正しい行動に導く」という意識を忘れないようにしましょう。
大声を出して子どもに恐怖心を与えてしまうと、その場だけを繕おうとしたり、親の顔色をうかがってしまったりする癖がつきやすくなります。しかるときは子どもが理解できるように、わかりやすく短時間で伝えましょう。
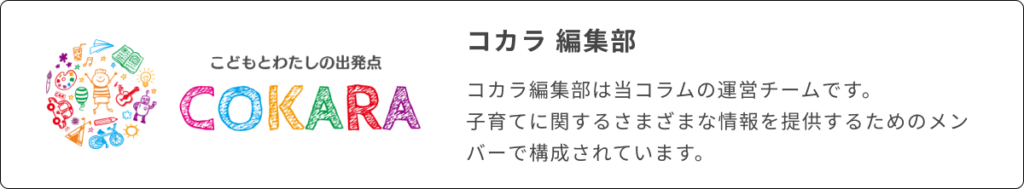



コメント