子どもを預けて働く・小学校までは家庭と幼稚園で教育するなど、家庭の状況や子どもの発達に応じて最適な施設は異なります。最適な施設を選ぶには、それぞれの園の基準や違い、選び方について理解しておく必要があります。この記事では、認定こども園と保育園、幼稚園の違いや預けられる基準などを解説します。
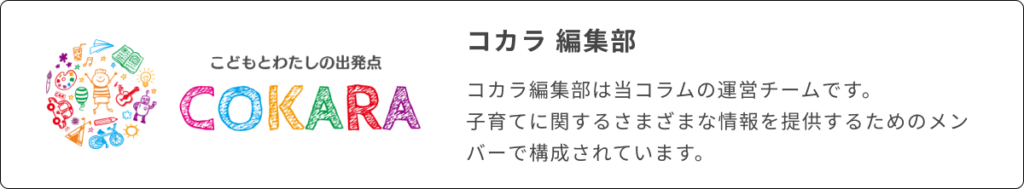

認定子ども園と保育園の違い
認定子ども園と保育園、幼稚園は管轄している省庁や設置目的が大きく異なります。子どもをいずれの施設に預けることを希望する場合、それぞれの違いを理解しておくことは非常に重要です。
1.認定こども園
認定こども園は、保育園と幼稚園が一体化したような施設です。そのため「幼保一体型施設」と呼ばれる場合もあります。本来の保育園としての役割(保育の必要性がある子どもの保育)に加えて、教育についても取り入れられています。
また幼保一体型となるため、親の状態に関わらず利用可能です。管轄省庁は内閣府が主導し、厚生労働省と文部科学省も関わっています。
2.保育園
保育園は親が仕事や介護、病気などの理由で「保育の必要性」が認められたときに利用できる施設です。そのため、保育園ではしつけや食事に関すること、排泄なども保育内容に含まれています。
保育時間などは、親の就業状況や保育認定によって異なります。また、認可外保育園などは利用するための基準が違うことに注意が必要です。管轄省庁は厚生労働省です。
参考:保育関係 |厚生労働省
3.幼稚園
幼稚園は、子どもの教育を提供する場としての役割を果たす施設です。管轄省庁は文部科学省です。そのため、身の回りの保育やしつけは保護者が行うことを前提としています。
幼稚園ごとに特色が異なり、親が通わせる施設を選択でき、就業状況などに制限はありません。また、最近では子育て支援を目的として2歳児の保育を実施している幼稚園も増えています。

それぞれのメリット・デメリットを知ろう
それぞれの施設の違いについて理解したところで、メリットやデメリットについて説明します。施設の良し悪しは親の就労状況によって異なりますので、それぞれの違いについても理解しておきましょう。
1.認定こども園のメリット・デメリット
認定こども園のメリットは、幼稚園と保育園のいいところを受けられることです。保育と教育の両面で子育てをサポートしているのが特徴で、保育所のように親の就労状況に変化があっても、保育時間の変更や転園の必要がありません。
デメリットとしては、全国的に見ても施設数は少ない傾向にある点です。教育に関する費用がかかることや、平日に参観・保護者会が予定されることなどもデメリットに挙げられます。
2.保育園のメリット・デメリット
保育園のメリットは0歳から子どもを預けられ、夏休みなどの長期休暇はなく、1年を通じて子どもの保育が受けられる点です。ほかにも、しつけや排泄に関することも保育内容の一部であり、サポートを受けられます。
デメリットとしては、週に一回タオルやシーツなどの身の回りのものを整えるなどの負担が大きいことです。さらに、登園時間は世帯によって異なるため、ほかの保護者と話す機会はあまりない点もデメリットに感じやすい点でしょう。
3.幼稚園のメリット・デメリット
幼稚園のメリットは、読み書きや計算などの基礎的な教育を受けられることです。ほかにも英語やリトミックに力を入れている幼稚園もあり、集団生活を送るうえで大切になる礼儀なども身につけられるでしょう。
デメリットとしては、認定こども園や保育園と比べて行事が多く、準備の負担が大きいことです。延長保育には別途費用がかかるため、夏休みなどは出費がかさむことなどが挙げられます。

どの園に入ればいい?それぞれの入園基準をチェック
園ごとに入園できる年齢や預けられる時間は、以下のように異なります。
【認定こども園】
- 対象年齢:0歳〜
- 保育時間:4〜11時間(保護者の就業状況で異なる)
- 年間保育日数:施設ごとに異なる
【保育園】
- 対象年齢:0歳〜
- 保育時間:8〜11時間(保護者の就業状況で異なる)
- 年間保育日数:300日
【幼稚園】
- 対象年齢:満3歳〜
- 保育時間:4時間程度
- 年間保育日数:39週以上

認定こども園や保育園、幼稚園の選び方
認定こども園や保育園、幼稚園の選ぶ際、以下の6つのポイントを意識しましょう。
- 保育内容が合うか
- 保育士や幼稚園教諭との相性
- 通いやすい距離か
- 送迎の有無
- 給食設備
- 特別支援保育へ対応しているか
いずれの園に入る場合も検討しておくべきポイントは同じです。それぞれに分けて選び方について詳しく解説しますので、見ていきましょう。
1.保育内容が合うか
保育内容は施設の種類ごとに大きく異なります。とくに幼児教育では義務教育よりもカリキュラムが多彩な傾向にあります。そのため「どのような保育内容を提供しているのか?」「子どもに無理をさせないか?」をしっかりと検討することが重要です。
多くの園では、Webサイトなどで保育・教育内容を公開していますが、可能な限り子どもを連れて見学してから通園する施設を選びましょう。
2.保育士や幼稚園教諭との相性
小さい子どもは、自分で考えや思いを上手に伝えられません。そのため、子どもの様子を観察して心配になった場合、先生に園での様子を気兼ねすることなく聞けると安心感を得られます。
また、子どものしつけや発達などを話し合いながら、家庭と園が一緒になって子育てできることが理想的だといえるでしょう。そのような関係性を築くには、見学時の会話を通じて保育士や先生との相性を確認することが重要です。
3.通いやすい距離か
園は数年通うことになるため、通いやすい距離にあるのかを確認しておくことが重要です。自宅から保育園や幼稚園が近ければ、送迎の時間を短縮でき、親子ともに負担を最小限に抑えられるでしょう。
また、子どもが小さい頃は体調が急に悪くなることや高熱を出してお迎えの電話がかかってくることがよくあります。そのような状況になっても、すぐにお迎えに行けると便利です。
4.送迎の有無
幼稚園や認定子ども園の場合、送迎手段のひとつにバスがあると便利です。送迎の負担が減れば、保護者も朝の忙しい時間に少しゆとりが出てくるでしょう。
また送迎バスがあると、少し離れた公園に遊びに行ける・園の行事などの行動範囲が広がるなどのメリットがあります。家庭の事情や都合に合わせて送迎の有無を確認しましょう。
5.給食設備
給食設備は、認可保育園や幼保連携型認定こども園には欠かせないものです。しかし、幼稚園などでは給食設備を持たずに外部サービスを利用していることもあります。
最近では、給食サービスの質も高まってきているため、食事の味の心配は少ないかもしれません。しかし、子どもにできたての温かい食事を食べさせてあげたいと考える人は、給食設備の有無を確認しておくとよいでしょう。
6.特別支援保育へ対応しているか
特別支援保育が必要な子どもには欠かせないポイントですが、支援の必要がない子どもでもチェックしておくとよいでしょう。
特別支援保育は、子どもの特性に合わせた「ていねいな保育」だとも言い換えられます。つまり、特別支援保育へ対応していることは、すべての園児を大切にしていると考えられます。

認定こども園と保育園の違いに関するよくある5つの質問

認定こども園と保育園の違いに関するよくある質問には、以下の5つが挙げられます。
- 質問1.通園する施設は見学した方が良い?
- 質問2.認可保育園と認可外保育園の違いは?
- 質問3.待機児童は多い?
- 質問4.途中入園は可能?
- 質問5.子育てと仕事を両立させるポイントを知りたい
ここではそれぞれの質問ごとの回答を解説しますので、詳しく見ていきましょう。
質問1.通園する施設は見学した方が良い?
通園を希望する施設には、可能な限り見学に行くことをおすすめします。実際に訪れることで、ホームページや案内パンフレットだけでは知り得ない雰囲気などを感じ取ることができるでしょう。
園児の様子や保育士の態度、クラスの清潔さなどは目で見なければわかりません。新規で開園することが予定されていて見学できない場合以外は、可能な限り足を運ぶように心がけましょう。
また、その際に不安となるのが「いつから見学できるのか?」「どのように電話で連絡すればよいのか?」ということではないでしょうか。これらのような不安を感じる方は以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
関連記事:保育園の見学はいつから行くべき?依頼するまでの流れもわかりやすく解説
関連記事:保育園見学前の電話のかけ方は?確認しておきたいことから見学の事前準備まで解説します
質問2.認可保育園と認可外保育園の違いは?
認可保育園と認可外保育園の違いは、国が定めた基準を満たしているか否かが大きな違いです。
認可保育園は児童福祉法に基づいた設置基準を満たし、都道府県から認可を得ている福祉施設との位置付けです。
一方の認可外保育園は基準を満たしていないため、認可を受けていない施設といえます。認可外保育園は多様化する保育ニーズに応えるために、幼児英語や休日・夜間保育など、特色あるサービスを提供している場合が多い傾向にあります。
それぞれ保育園ごとの違いについて気になる方は、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
関連記事:認可保育園とは?保育料を決める要素やメリット、デメリットを紹介!
関連記事:認可外保育園とは?認可保育園との違いやメリット、デメリットを徹底解説
質問3.待機児童は多い?
厚生労働省が令和4年4月に公表している「保育所等関連状況取りまとめ」を参考にした待機児童の数は2,944人です。これは前年同月と比較すると2,690人減少した数値です。
待機児童が減少した背景には、国の取り組みである「子育て安心プラン」の成果が出た結果だといえるでしょう。
しかし、保育ニーズの高まりは今後も予測されているため、再び待機児童が増加しないとも限りません。
参考:保育所等関連状況取りまとめ(令和4年4月1日)及び「新子育て安心プラン」集計結果を公表
待機児童に関する最新情報は、以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方は参考にしてみてください。
関連記事:待機児童の現状は?具体的な数値から問題解消が難しい3つの理由まで解説
質問4.途中入園は可能?
途中入園は可能ですが、実際にできるかどうかは各施設によって異なります。途中入園ができるのは、保育できる園児の枠が空いている場合に限られてるため、通常よりも難しい傾向にあります。
途中入園に関する情報は、認定こども園や保育園が独自に運営するWebサイトや自治体が公表しています。また、最近ではSNSで途中入園に関する情報を投稿している場合も見受けられますので、幅広く探してみると希望する条件の園を見つけやすいかもしれません。
保育園の途中入園に関することが気になる方は、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
関連記事:保育園の途中入園は可能?入りやすい時期からメリット、探し方まで徹底解説!
質問5.子育てと仕事を両立させるポイントを知りたい
子育てをしながら働くのは大変ですが、周囲の理解と協力を得られれば不可能なことではありません。そのために大切になるのが環境づくりです。保育園はもちろんのこと、パートナーや自治体で使える保育制度、両親など頼れる存在をひとつでも多く増やすように行動しましょう。
子育てをしていると、自分が子どもを迎えに行けない状況や病気に罹ってしまうことも当然あります。その際、スムーズにサポートしてくれる存在があるだけで仕事と子育ての両立がしやすくなります。
ほかにも子育てと仕事を両立させるために知っておきたいことは、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:子育てと仕事を両立させる5つのポイントを紹介!働きやすい仕事の特徴も解説!

まとめ
認定保育園や保育園、幼稚園の違いについて解説しました。各施設は目的等が異なり、家庭状況に応じた施設を選ぶことが通い続けるために重要だといえます。
一番大切なのは「子どもに合った園なのか」ということです。まずは大まかに認定こども園・保育園・幼稚園の違いを理解し、希望する施設を探して見学すると最適な選択ができるでしょう。
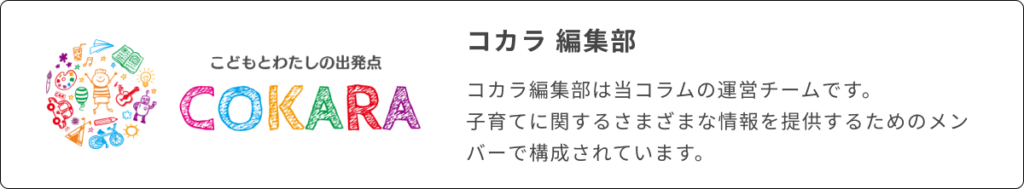



コメント